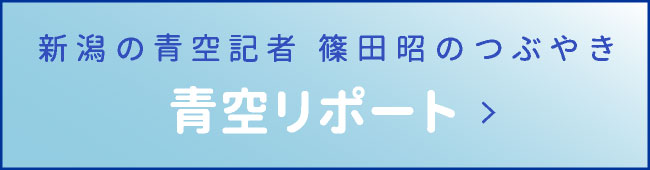Vol.18
大森前橋国際大学長が本学園で講演㊦ ―「地域と向き合い、少子化と向き合う」―
―地方私大の今後の取り組みを明示―
<地域で生きる覚悟と行動>
共愛学園前橋国際大学の大森昭生学長のご講演の紹介を続けます。
後半は「中教審の答申を踏まえて、地方私大はどう生き残りの道を探るのか」がテーマです。私にとって最も切実であり、また日本全国どの学園にとっても現在の最大のテーマと思います。大森学長はその難題について、「これからの地方大学が取り組まなければならないこと」とのタイトルで熱っぽく語り始めました。
大森学長は「地域は学生たちが受け入れてもらい、生きる場」であると規定し、「地域で必要とされない大学が生き残れるはずがない」との大きな前提を示されました。(青陵では「青陵プロミス」として、「地域から青陵があってよかった!」と思っていただくことを〝地域へのお約束〟としています。今後は「地域は学生たちの生きる場」としての視点を付加しようと思います)そして、「地域で生きる覚悟と行動」を3分野からまとめられました。
<地域との関係を築くには‥>
1つ目は「地域との関係はそう簡単じゃない」との〝念押し〟です。点検ポイントは5つ。①地域で草むしりをしていますか? ②教職員は地元で暮らしていますか? ③学生たちが真ん中にいますか? ④組織ではなく個人と繋がっていますか?そして、⑤こちらから出向いて行っていますか?―です。
2つ目は「地元産業界がこちらを向いてくれない」―との学園側の〝嘆き〟についてです。ここのチェックポイントは3つ。①経済同友会、商工会議所、中小企業家同友会などに参画して活動していますか? ②個々の社長や社員と関係がありますか?そして③飲み会に参加していますか―の3点です。
3つ目は「自治体や教育委員会は国公立ばかりを見ている」との学園側の〝不満〟です。これは私も新潟市長時代によく聞かされた愚痴でした。この点検も3点。①何でも「承知しました!」と引き受けていますか? ②大学の教育改革が高校の半歩先を行っていますか? ③地方創生総合戦略や教育振興基本計画、指導要領を読んでいますか?―でした。私たち学園の人間が今回の中教審答申も読まずに「大学・短大のこれから」を考えても、どうしようもないということですね。
<少子化が招く「2つの怖いシナリオ」>
全国の大学の6割が定員割れに陥っており、今後はさらに少子化が本格化してきます。大森学長は群馬県の18歳人口(17550人)と出生数(9950人)の数字を挙げて、深刻度(減少率44%)をお伝えになりました。新潟県で言うと直近の18歳人口が18600人なのに対し、昨年の出生数は10500人。減少率は同じく44%です。群馬も新潟も18年で半分近くに減ってしまうのです。
「このままでは大学、特に私大が地方から消えていき、そのことによって2つのことが起きる」と大森学長はシナリオを整理します。
1つは地方の若者が地方の大学に行けなくなって大都市圏に進学するようになり、若者が大都市圏に集中します。その結果は「地域力の低下」に直結します。
もう1つは、地方の大学(特に私大)に通えなくなった若者のかなりの部分は経済的な理由などで大都市圏の大学には通えないため、日本の大学進学率が低下し、その結果が「国力の低下」につながる、というものです。
<「地域構想推進プラットフォーム」設立を>
今後さらに厳しくなる少子化の中で大学に対する「大きな政策」を国や地方自治体が打ち出さなければ、間違いなくこの「2つのシナリオ」が進行します。(このことについては、「理事長室から」から入ってもらえる私のブログ「青空リポート・地方私大の役割」で紹介してありますので、是非ご覧ください)では、どうするか?大森学長は、「知の総和」答申で示された「各地域での高等教育機関へのアクセス」を確保するため、これも答申で言及されている「地域構想推進プラットフォーム」設置の重要性を訴えられました。
<「進学を望む者の立場に立てるか」>
「地域ごとのアクセス確保と人材育成のための〝協議体〟を地域のステークホルダー(産官学民と情報機関など)でつくっていく必要がある。それが地域構想推進プラットフォームです」と大森学長は言います。その時に「自分の大学だけは生き残りたい」と言っていては地域の共感は得られません。「大学・短大に進学を望む地域の人間の立場に立って、『地域の多様な高等教育機関に通えるアクセスを確保するため、私たちは大同団結する』と各大学・短大が言えるか―そこが問われる」と大森学長は言い、「極論すれば、『地域でのアクセスが確保できれば、自分の大学は残らなくともよい』と言えるぐらいの覚悟を決めないと、地域での協議は成功しない」と核心に迫ります。
「身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあれ」ではありませんが、超少子時代に学園が生き残っていくには、そのぐらいの覚悟と理念が求められる―ということでしょうか。
<何にどう向き合っていくのか?>
大森学長のご講演の締めくくりは、「この厳しい時代、私たちはこれから何にどう向き合っていくのか」を問いかけるものでした。向き合うものは4つでした。
まず、「少子化に向き合う」こと。<18年後の少子状態は数字で見えているのですから、もう先送りはできません>これは絶対的に必要です。
次いで「地域(自治体・産業界・地域住民)と向き合う」ことです。問われるのは<地域が地元大学を自分事化してくれるように動いているか>どうかです。
3番目は「(ほかの大学・短大などの)仲間と向き合う」です。<地元の子どもたちのために、もう、ライバルと言っていられない>と言うのです。ここが先ほどの「地元の進学希望者のために『自分の大学は残らなくてよい』と言えるか」―その覚悟が問われる部分です。当面、みんなにとってここが一番辛い問いかけではないでしょうか。
そして最後が「(大学を多くの方が本当に必要と思ってくれるかを問う)国民と向き合う」です。<私たちはこれまで、国民が「大学は必要」と言ってくれるような働きかけをしてきただろうか>、<私立大学は儲け主義という誤解を解いてきただろうか>、<大学は社会のインフラだという国民的理解を醸成してきただろうか>―この3つの問いかけは重く、私たち学園に所属する者の心に響きます。
<聞きっぱなしにはできない>
大森講演は心に残る大変に素晴らしいものでした。ただ、これを聞いただけで終わらせてしまっては意味がありません。「これから何にどう向き合い、行動していくかが問われます。
幸い、今回の大森講演には新潟県内の私立大学・短大の多くの理事長・学長が参加してくれていたので、講演の後、早速「作戦会議」を開きました。まず、少子化による「地方の大学・短大の窮乏」は地域の方にとって他人事ではなく、「地域の衰亡」に直結するもの―との意識を自治体や経済界などにも共有してもらう必要があります。「そのためにも、新潟で地域構想推進プラットフォームを設置しよう」「それにはまず、花角県知事に面談し意見交換する必要がある」―との方向で多くの理事長・学長が一致しました。
今後は、できるだけ早く花角英世知事の日程をいただき、地域構想推進プラットフォームの設置について話し合えるよう、日程調整に入っていただいています。できるだけ早期に「新潟版・地域構想推進プラットフォーム」を設置し、全国から「新潟モデル」と言われるような実績を出していく気概で取り組んでいきたいと思います。
今後もご助言・ご支援をお願いします。

2025年4月25日
新潟青陵学園理事長 篠田 昭